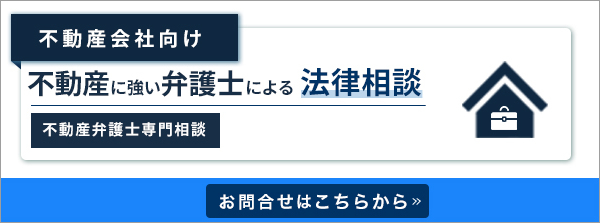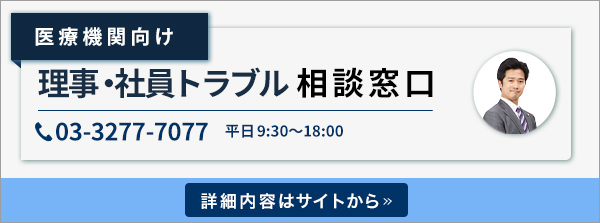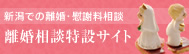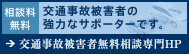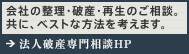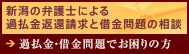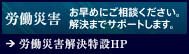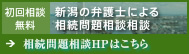(つづきはしばらくお待ちください。)
今回の連載では、海外展開について自社で海外用の製造ラインを設けるのはコスト的に難しいものの、なんとか海外に進出できないだろうかという場合に、ライセンス契約を用いて海外展開をする際の必要な検討項目について説明します。
今の情報社会ではライセンス契約の利点がより際立つようになりました。
パートナーが必要な製造設備さえ有していれば、情報を渡すだけで直ちに製造に進むこともでき、利益を出すまでの行程が非常に短くなる傾向にあります。
また、ライセンサーとなる自社は製造行為を行わないため、製造に必要なラインや従業員の確保も不要で、製品の移送といった諸手続に伴うコストもカットできるという利点もあります。
しかしながら他方で、一度情報を渡してしまった結果、技術が流出したり、模倣品の製造を許してしまったりといったようなリスクも伴います。
そのような自社技術の取り扱いについてどのような点に注意すればよいのでしょうか。
ライセンス契約を基本とする場合の事前準備
まず、ライセンス契約を基本とする手法を採用する場合は、海外展開に関わる自社技術について整理と確認の作業が不可欠です。
第1回のNDAについての記載と重複しますが、技術情報というのは大きく2つに分けられます。
1つは、自社の資産とするには情報をオープンにする必要がある情報です。
例えば、特許権や商標権といった権利は、情報を特許法や商標法が定める手続を経て、公開することによって権利が認められ、ライセンスの対象として価値を帯びるということになります。
もう1つは、公開されていないからこそ、社内秘として価値を帯びているような情報です。
いわゆる社内情報やノウハウ、特許等の取得を行っていない技術情報などはこちらの類型に該当します。
このような大きく2つの分類があることを前提に、海外展開製品が主にどちらの類型の情報を利用して製造されているのか確認する必要があります。
前者の場合、すなわち、自社特許製品について海外展開を考えている場合は、技術自体が特許公報などにより公開されている状態のため、技術流出や模倣品対策などを考えるコストは抑えつつ、むしろ展開先の知的財産法に照らし、当該特許が有効に成立しているのか、後々に覆されたりすることがないか、といったことの確認にリソースを割くべきです。
国によってはライセンス契約を行政機関に報告する必要がある可能性もありますので、そのような周辺情報も事前準備の範囲に入ってきます。
後者の場合は、自社しか知り得ない情報を相手方に渡すことになるため、技術流出対策を徹底したり、相手方の情報管理体制の確認をしたりといった秘密の保持を中心にリソースを割くことになります。
また、ノウハウの中にはいわゆる熟練技術のような客観的には表現しにくいコツのような情報も含まれます。
自動車の操作方法書を知ったからと言って自動車をすぐに運転することができない、楽譜をみても楽器をすぐには演奏できないといったことなどがイメージとしては分かりやすいです。
このような場合は、ライセンスの対象をいかに表現するかという難しい事項が関連しますし、どうすれば相手方が製造を開始できるかというプランニングにも注力が必要です。

ライセンスの対象が決まると、次に考えなければならないのが、対価であるロイヤリティになります。
一般的には、イニシャルロイヤリティ、ランニングロイヤリティ、ミニマム(マキシマム)ロイヤリティ、といった対価の種類があります。
ですが、このような種類がある一方、詳細な定義においては全く統一されているとは言えず、契約によって各々違うという認識をもっていた方がよいでしょう。
イニシャルロイヤリティはライセンス契約締結時に支払う技術利用を認めたことに対する対価になります。
ランニングロイヤリティは、ライセンス対象技術を利用したことでライセンシーが得た利益に対する対価。
ミニマム(マキシマム)ロイヤリティは、ランニングロイヤリティの下限(上限)を決めるものになります。

ライセンス契約の注意点
最後に、簡単にライセンス契約締結時の注意点を挙げておきます。
それは税法との関係です。
ロイヤリティの相場を押さえていなければ税法上、不当に又は過大にロイヤリティを支払っている(ラインセンスを与えている)として、適正価格に引き直された上に、想定外の課税を受ける場合があります。
経営者として合理性の説明を求められるというリスクも考えられます。
また、税に関連して誰がどのタイミングで徴収を受けるのかということも確認が必要です。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2018年12月号(vol.227)>
*本記事は2018年12月執筆時での法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
*記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。
* 当事務所は、本サイト上で提供している情報に関していかなる保証もするものではありません。本サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。
* 本サイト上に記載されている情報やURLは予告なしに変更、削除することがあります。情報の変更および削除によって何らかの損害が発生したとしても、当事務所は一切責任を負いません。